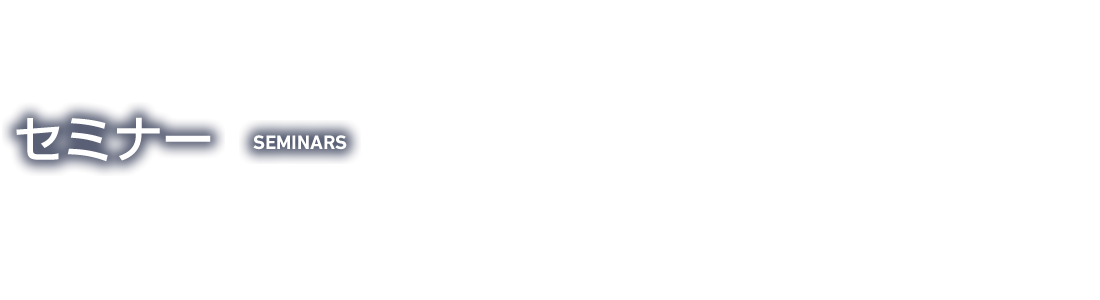6月8日(木) セミナー会場1・2・3 定員80名
| セミナー会場1 | セミナー会場2 | セミナー会場3 | |
|---|---|---|---|
| 10:20~11:20 |
関西大学 登録受付を終了いたしました |
大阪府警察本部 府民安全対策課 登録受付を終了いたしました |
国土交通省 近畿地方整備局 登録受付を終了いたしました |
| 11:40~12:40 |
大阪管区気象台 登録受付を終了いたしました |
大阪府警察本部 特殊詐欺対策室 登録受付を終了いたしました |
「事業継続計画(BCP)策定支援制度のご紹介~地震や風水害に負けない組織作り~」 大阪府商工会連合会 事業継続計画策定支援研究委員会 委員長 登録受付を終了いたしました |
| 13:00~14:00 |
「南海トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動に関する政府の検討内容について」 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当) 登録受付を終了いたしました |
5団体防犯建物部品普及促進協議会 登録受付を終了いたしました |
大阪市消防局 登録受付を終了いたしました |
| 14:20~15:20 |
農林水産省 登録受付を終了いたしました |
日本赤十字社大阪府支部 登録受付を終了いたしました |
第五管区海上保安本部 登録受付を終了いたしました |
| 15:40~16:40 |
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 登録受付を終了いたしました |
立正大学 教授 登録受付を終了いたしました |
「熊本地震、糸魚川大火、常総市水害に共通する危機管理の意外な盲点」 株式会社新建新聞社 登録受付を終了いたしました |
6月9日(金) セミナー会場1・2・3 定員80名
| セミナー会場1 | セミナー会場2 | セミナー会場3 | |
|---|---|---|---|
| 10:20~11:20 |
関西広域連合 広域防災局 登録受付を終了いたしました |
住宅侵入犯罪等抑止対策協議会 登録受付を終了いたしました |
大阪教育大学 大阪教育大学 大阪教育大学 登録受付を終了いたしました |
| 11:40~12:40 |
大阪府 登録受付を終了いたしました |
大阪府警察本部 登録受付を終了いたしました |
プチハウスなな/LLPユニバーサルデザイン企画 登録受付を終了いたしました |
| 13:00~14:00 |
「南海トラフ地震に立ち向かう高知県の挑戦~命を守る対策の徹底、命をつなぐ対策の加速化へ~(仮題)」 高知県知事 登録受付を終了いたしました |
登録受付を終了いたしました |
「鈴与グループの事業継続の取り組み ~事前対策、訓練事例の失敗例を含めて~」 鈴与株式会社 危機管理室 室長 登録受付を終了いたしました |
| 14:20~15:20 |
文部科学省 研究開発局 登録受付を終了いたしました |
日本赤十字社大阪府支部 登録受付を終了いたしました |
一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会 登録受付を終了いたしました |
| 15:40~16:40 |
大阪管区気象台 防災調査課 調査官 登録受付を終了いたしました |
「『災害からの安全な京都づくり条例』と災害危険情報の整備・提供について」 京都府 登録受付を終了いたしました |
「熊本地震の教訓と被災地の復興」
昨年発生した熊本地震の教訓は、応急対策と生活支援に関して、政府のワーキンググループで検討された。8章からなる報告書は、最初の4章は直接の教訓が書かれ、残りは将来、南海トラフ巨大地震が起こった時を想定してまとめられている。その内容を概説するとともに、熊本県や益城町などの被災地の復興計画がどのようなものかについて報告する。

講師
関西大学 社会安全学部・社会安全研究センター長・特別任命教授
河田 惠昭氏
講師略歴
関西大学社会安全学部・社会安全研究センター長・特別任命教授(チェアプロフェッサー)。工学博士。専門は防災・減災。現在、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長(兼務)のほか、京大防災研究所長を歴任。京都大学名誉教授。2007年国連SASAKAWA防災賞、09年防災功労者内閣総理大臣表彰、10年兵庫県社会賞、14年兵庫県功労者表彰、16年土木学会功績賞、17年アカデミア賞受賞。現在、中央防災会議防災対策実行会議委員。日本自然災害学会および日本災害情報学会会長を歴任。
「防災気象情報の改善について」
近年、集中豪雨や台風等による被害が相次いで発生しており、また、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しています。このため、気象庁では『可能性が高くなくともその発生のおそれを積極的に伝える』、『危険度の高まりを伝える』、『実況を迅速に伝える』ことを目的に、住民の皆さまに自らの地域に迫る危険を納得感を持って把握できるよう改善を進めていますので、その改善点等について紹介します。

講師
大阪管区気象台 予報課 水害対策気象官
西村 修一氏
講師略歴
1982年 気象庁入庁
2016年 大阪管区気象台 予報課 水害対策気象官
「南海トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動に関する政府の検討内容ついて」
超高層ビルを大きく揺らす長周期地震動は、規模の大きな地震で強く励起される。2011年東北地方太平洋沖地震では、震源から遠く離れた大阪の超高層ビルでも長周期地震動による揺れが報告されている。近い将来に発生が懸念される南海トラフ巨大地震でも長周期地震動の影響が懸念される。本セミナーでは、内閣府が一昨年公表した「南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告」を中心に、政府の検討内容を紹介する。

講師
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当)
参事官補佐
岩村 公太氏
講師略歴
2003年気象庁入庁。同庁気候・海洋気象部気候情報課、予報部数値予報課、文部科学省研究開発局海洋地球課、気象庁総務部企画課、地震火山部管理課を経て、2017年4月から現職。南海トラフ沿いの巨大地震、首都直下地震等、政府の中央防災会議が検討対象とする巨大地震対策を担当。
「食料の安定的な確保〜災害時の支援と家庭備蓄〜」
地震等の大規模な災害時には、食料供給の減少などが予想されます。
農林水産省が行う災害時の食料支援の取組みや、家庭等での備蓄(最低でも3日分出来れば1週間分程度)の必要性について、事例も紹介しながらお話します。
あわせて、現在の国内外の食料需給の状況や食料の安定供給のために農水省が平時から行っている取組についても紹介します。
講師
農林水産省
食料安全保障室 食料安全保障専門官
清水 友和氏
講師略歴
2001年農林水産省入省、食品製造業の衛生管理の向上支援、食料・農業・農村白書などの担当を経て、2016年6月より現職。平時からの食料供給に係るリスクの評価・分析、食品小売価格動向調査、家庭備蓄の推進、不測時の政府の対策(緊急事態食料安全保障指針)を担当。
「ドローンの災害時における利活用について」
災害時にドローンを利活用するためには、災害時にドローンを利活用できる技能を有した人材が現地に存在する必要があります。こと災害時に関しては臨機応変な現場の対応が要求され、2次災害のリスクも伴いますので、高度な安全に関する知識と技能が不可欠です。
JUIDAでは、これまで全国70校以上の認定スクールから、1000名以上のJUIDA安全運航管理者を輩出してきました。全国JUIDA認定スクールの拠点ネットワークや全国JUIDA安全運行管理者の人的ネットワークは、災害時にドローンを利活用できる強力な仕組みです。現に、既にいくつかのJUIDA認定スクールが、地域自治体と災害対応協定を結んだ例がございます。当日の講演は、その具体例を紹介しながら、ドローンを災害時に利活用できる仕組みについて紹介致します。

講師
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)
常務理事
岩田 拡也氏
講師略歴
1998年通商産業省工業技術院電子技術総合研究所に入所。第16回電子材料シンポジウムEMS賞受賞、第12回応用物理学会講演奨励賞受賞。白色LED開発にてゼロから1兆円産業に成長する過程を経験。半導体製造装置開発からロボット技術に目覚め、2004年に独立行政法人産業技術総合研究所知能システム研究部門に移籍、無人航空機の研究開発をスタート。2007年日本機械学会交通・物流部門優秀講演表彰を受賞。2008年に経済産業省製造産業局産業機械課にてロボット政策に従事。2009年以降「NIIGATA SKY PROJECT」の無人航空機開発を立ち上げる。
「企業における防犯CSR活動について」
CSR(Corporate Social Responsibility)とは、一般的に「企業の社会的責任」と言われており、企業が社会の一員として果たすべき様々な責任を意味する。
近年、多くの事業者等により、環境保全や社会福祉、防災など様々な分野で積極的なCSRが行われているが、犯罪の被害防止など地域の安全・安心に貢献するため、防犯に関するCSR活動に取り組んでいる企業の活動を紹介する。
講師
大阪府警察本部 特殊詐欺対策室
特殊詐欺対策担当補佐
馬郡 清高氏
「大阪における特殊詐欺被害の現状と被害防止について」
大阪府下における振り込め詐欺など特殊詐欺の被害は年々増加傾向にあり、平成28年中の被害は認知件数が1,633件にもなり、被害総額は約52億6千万円にのぼるなど、ともに過去最悪を記録し、非常に厳しい状況にある。
このように多発する特殊詐欺の現状や被害の多い手口を知ってもらい、被害に遭わないためのポイントなどについて紹介する。
講師
大阪府警察本部 特殊詐欺対策室
特殊詐欺対策担当補佐
橋本 浩伸氏
「我が家を守るCP製品!」
"生命や財産を守るのは自分たちであり、各地域の実情にあわせた防犯対策が、多くの生命や財産を守るために大きな役割を果たすことになります。
防犯対策は自主防犯が基本であり、各家庭の開口部の確認が重要です。また、近隣コミュニティの協力も欠かせません。
まず、各家庭でできる対策を整え、いざという時のためにCP商品で備えましょう。
講師
5団体防犯建物部品普及促進協議会
業務部長
遠藤 和夫氏
講師略歴
2012年 7月 (一社)日本シヤッター・ドア協会へ嘱託として入会。〔前職 三和シヤッター工業(株)〕
防犯(CP)製品を扱う協会委員会(ドアB種、軽量・重量シャッター、OHD、窓シャッター)に携わる。協会会員や会員外からのCP型式承認申請、仕様変更などに対し、防犯性能の試験の実施や裏付け確認をおこない、官民合同試験委員会へ申請しCP目録登録をおこなっている。
2017年 4月 現在に至る。
「熊本地震における日本赤十字社大阪府支部の活動について」
日本赤十字社大阪府支部では、熊本地震の発生後、直ちに医師・看護師等で構成された救護班を派遣し、甚大な被害を受けた南阿蘇村に仮設診療所(dERU)を設営し、医療救護活動を行いました。
現地では、約1カ月に渡り、甚大な被害を受け孤立した南阿蘇村の医療を支えてきました。
発生直後の南阿蘇村がどのような状態だったのか、日赤がどのような医療救護活動を行ったのかを紹介します。

講師
日本赤十字社大阪府支部
事業課 救護係長
中川 俊彬氏
講師略歴
日本赤十字社大阪府支部において、災害救護活動に関する業務に従事している。平時は、災害救護資機材の整備、研修会や救護訓練の実施、計画の作成などに携わっているが、災害発生時は、医療救護班の一員として被災地に行き、災害救護活動の連絡調整等を実施する。
主な救護活動履歴
東日本大震災(宮城県仙台市)、熊本地震(熊本県南阿蘇村)
「防犯の世界標準『犯罪機会論』とは何か」
犯罪原因論は「なぜあの人が」というアプローチから動機をなくす方法を探求するが、犯罪機会論は「なぜここで」というアプローチからチャンスをなくす方法を探求する。つまり、動機があっても、犯行のコストやリスクが高くリターンが低ければ、犯罪は実行されないと考えるわけだ。海外では当たり前のように実践されている犯罪機会論が、日本ではほとんど知られていない。そこで本セミナーでは犯罪機会論を分かりやすく紹介したい。

講師
立正大学 教授
小宮 信夫氏
協力:株式会社セキュリティ産業新聞社
講師略歴
ケンブリッジ大学大学院犯罪学研究科修了。法務省、国連アジア極東犯罪防止研修所などを経て現職。専攻は犯罪学。地域安全マップの考案者。警察庁「持続可能な安全・安心まちづくりの推進方策に係る調査研究会」座長などを歴任。代表的著作は『写真でわかる世界の防犯 ——遺跡・デザイン・まちづくり』(小学館)。
「近畿地方整備局における防災対策」
我が国の国土は、各国と比較すると極めて厳しい状況下にあり、毎年のように自然災害が発生している。
近畿地方整備局では、種々の大規模災害にも対応できるよう計画を定めるとともに、平時から訓練を重ね、災害に備えています。
また、昨年度の災害対応状況報告(TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)活動)を行う。
講師
国土交通省 近畿地方整備局
総括防災調整官
梅敷 寛氏
講師略歴
昭和59年国土交通省(当時建設省)入省。主に河川を担当。
平成7年阪神淡路大震災では、兵庫県内の急傾斜地緊急調査に参加。
また同じく阪神淡路大震災で河川堤防が被災した教訓を踏まえ、淀川において耐震補強事業を展開。
度重なる家屋浸水が発生していた新宮川、由良川沿川において、水防災対策特別事業の調整を実施。
紀の川ダム統管の所長等河川管理業務を経験し、平成29年4月から現職。
地震、洪水、雪害など各災害時備え、近畿地方整備局で防災実務の総括をとる。
「事業継続計画(BCP)策定支援制度のご紹介〜地震や風水害に負けない組織作り〜」
鬼怒川の氾濫を引き起こした一昨年の関東・東北豪雨や昨年の熊本地震では、多くの企業が深刻な被害を受け、事業継続に大きな影響を及ぼしました。これを受け、BCP策定に取り組む企業が年々増加するとともに、策定済みの企業においては見直しや訓練を行う動きが活発化しています。本セミナーでは、BCP策定ならびに見直しや訓練における留意点をお伝えするだけでなく、それらの取組みにご活用頂ける支援制度をご紹介致します。

講師
大阪府商工会連合会 事業継続計画策定支援研究委員会 委員長
ミネルヴァベリタス株式会社 代表取締役
松井 裕一朗氏
講師略歴
外資系企業・国内企業・官公庁における各種リスクマネジメント(事業継続、防災、危機管理など)に関するコンサルティングに従事する一方、自治体などの有識者会議の委員としての活動も行う。革新的な事業継続の取り組みを称える国際的な賞である「The BCI Asia Awards」を2年連続(2015年、2016年)で受賞。
■英国事業継続協会(BCI)プロフェッショナルメンバー
■大阪市新型インフルエンザ等有識者会議 委員
■大阪府商工会連合会 事業継続計画策定支援研究委員会 委員長
「災害救助の最前線」
大阪市内で発生した火災や人命救助事案をはじめ過去の災害事例をもとに、救助隊員が災害現場における人命救助活動に必要な知識及び技術を、わかりやすくかつ実践を交え解説するとともに、最近の事例を紹介しながら災害救助の最前線に迫ります。
講師
大阪市消防局
警防部警防課 副課長
山下 伸也氏
「大規模災害発生時における海上保安庁の対応について」
海上保安庁救難体制、災害時の活動状況の紹介
講師
第五管区海上保安本部 関西空港海上保安航空基地
警備救難課 上席機動救難士
今川 豪氏
講師略歴
H9. 海上保安庁入庁
巡視船勤務を経て、特殊救難隊
H24. 特殊救難隊長
H28. 関西空港海上保安航空基地(現職)
「熊本地震、糸魚川大火、常総市水害に共通する危機管理の意外な盲点」
熊本地震、糸魚川大火、常総市水害の取材で現地を歩くなか、全く違う災害ながら意外な危機管理における共通の盲点が見えてきました。多数の企業や自治体の危機管理を取材してきた記者が、具体的な事例を交えながら解説します。
講師
株式会社新建新聞社
リスク対策.com編集長
大越 聡氏
講師略歴
大学卒業後、通信社などのメディアを経て、住宅設備機器メーカーで約10年危機管理広報、CSR広報に携わる。2014年からリスク対策.comに参加。企業や自治体の危機管理・BCP・防災の取材多数。
「関西広域連合の広域防災に対する取り組みについて(仮題)」
講師
関西広域連合 広域防災局
「熊本地震等の教訓を踏まえた大阪府の取組みについて」
本府では、「平成28年熊本地震」等の教訓を踏まえて、平成29年3月に大阪府地域防災計画の修正を行う等、様々な取組みを実施しております。その内容と取組状況について、説明します。
講師
大阪府
危機管理室 防災企画課
田中 一史氏
「南海トラフ地震に立ち向かう高知県の挑戦~命を守る対策の徹底、命をつなぐ対策の加速化へ~(仮題)」
南海トラフ地震による甚大な被害が想定される中、命を守る対策を最優先に進めるとともに、命をつなぐ対策や生活を立ち上げる対策にも全力をあげた高知県の取り組みを紹介します。

講師
高知県知事
尾﨑 正直氏
講師略歴
平成 3年 3月 東京大学経済学部卒業
平成 3年 4月 大蔵省(現財務省)入省
平成 9年 7月 国税局行田税務署長
平成10年 5月 外務省在インドネシア大使館
平成15年 7月 財務省 主計局主査
平成17年 7月 同 理財局計画官補佐
平成18年 7月 内閣官房副長官秘書官
平成19年10月 財務省退職
平成19年12月 高知県知事(1期目)
平成23年12月 高知県知事(2期目)
平成27年12月 高知県知事(3期目)
主な役職就任状況
内閣官房 教育再生実行会議 委員(平成25年1月〜)
同 ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会 委員(平成25年3月〜)
内閣府 子ども・子育て会議 委員 (平成25年4月〜)
同 基準検討部会 委員(平成25年4月〜)
内閣府 中央防災会議「防災対策推進検討会議」南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 委員(平成24年4月〜平成25年4月)
内閣府 大規模災害情報の収集・保存・活用方策に関する検討会 委員(平成27年2月〜)
内閣府 中央防災会議「防災対策実行会議」南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループ 委員(平成28年9月〜)
全国知事会 社会保障常任委員会 副委員長(平成24年7月〜)
同 次世代育成支援対策プロジェクトチーム リーダー(平成24年7月〜)
全国高速道路建設協議会 会長(平成27年6月〜)
日経ビジネス(2015.12.28・2016.1.4合併号)特集「次代を創る100人LEADER(逞しき指導者)に選出(平成27年12月)
「防災・減災のための科学技術研究の取り組み」
我が国は首都直下地震や南海トラフ地震など巨大災害の脅威に直面しています。またゲリラ豪雨や竜巻、豪雪などの極端気象災害も近年多発しています。災害を観測・予測し被害の軽減につなげるために文部科学省が実施する大型プロジェクト研究や海底地震・津波観測網の整備、防災科学技術研究所の取り組みについて紹介します。

講師
文部科学省
研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室長補佐
田中 大和氏
講師略歴
平成4年 建設省入省
平成20年 国土交通省国土地理院 基盤地図情報課長
平成22年 環境省生物多様性センター 情報システム企画官
平成24年 バングラデシュ人民共和国派遣 国際協力機構(JICA)専門家
平成27年 現職
「『JMA-MOT(気象庁機動調査班)』の活動について」
気象庁では、自然災害が発生した場合、被災地域周辺の状況把握や、現象の解説のための職員派遣を実施し、被災地等における迅速な活動及びその成果の周知・広報が重要であると考えています。 このため、これらの活動を『JMA-MOT(気象庁機動調査班)』の名称を用いて実施していますので、突風災害の調査を中心に紹介します。

講師
大阪管区気象台 防災調査課 調査官
山本 實氏
講師略歴
1986年 気象庁 入庁
2016年 大阪管区気象台 防災調査課 調査官
「防犯環境の整備に向けた取組について」
府下における、最近の犯罪情勢や防犯環境の整備に向けた取組等についての講演を行う。
特に、府警と住宅メーカー等にて組織される住宅侵入犯罪等抑止対策協議会が進めている「大阪府防犯優良戸建住宅」の普及等をはじめとする具体的な取組等を紹介し、犯罪に強い、安全安心なまちづくりの必要性、重要性についての講演を行う。
講師
住宅侵入犯罪等抑止対策協議会
大阪府警察本部 府民安全対策課 防犯環境担当 警部
荒木 学氏
講師略歴
大阪府警察本部において、防犯性能の高い住宅の普及や防犯カメラの設置促進等、安全安心なまちづくりに向けた防犯環境整備に関する施策の企画立案を担当している。
「テロ対策」
現下の国際テロ情勢は、ISIL、いわゆる「イスラム国」等のプロパガンダの影響を受けて過激化した者によるホーム・グローン型のテロが多数発生しており、 昨年発生したバングラデシュ・ダッカにおけるテロ事件では、邦人が被害に遭う等、我が国においても、いつテロが発生してもおかしくない情勢である。従って、こうした厳しい情勢を踏まえ、民間事業者や地域住民等と緊密に連携した官民一体型の「日本型テロ対策」を強化する。
講師
大阪府警察
警備総務課・課長補佐
椛島 勝氏
「震度7の生存確率」
この程幻冬舎から出版された「震度7の生存確率」を題材とした講演になります。
日ごろいわれている防災の常識の中には 最新の知見では多くの間違いがございます。
震度7に備えるにはどうすれば良いのか、また発災の瞬間に 貴方はどの様な行動を取るか、その危険度チェックを相対的な確率で表す画期的な内容です。
それによる身近にある、危険な場所・危険な物・危険な行動を改めて知る事になります。
また後半では、平成30年の学習指導要領の改訂の中で防災学習の義務化への動きに伴う防災教育の産業化に向けた取り組みの紹介等を致します。
講師
日本防災教育振興中央会
代表理事
仲西 宏之氏
主催:一般社団法人公共ネットワーク機構
協力:一般社団法人日本反射材普及協会
講師略歴
(株)防災教育振興研究所 所長 特定非営利活動法人ひろしま県防災教育振興協会
テイトクリストファー コネクトフリー(株) 代表取締役総合開発責任者兼CEO
「赤十字防災啓発プログラム」講習
毎年、世界のどこかで災害が起こり、数多くの人が様々な災害の犠牲になっています。中でも、日本は世界有数の地震大国と言われ、大きな地震による被害も経験しました。日本赤十字社大阪府支部では、これまでの多くの災害から学んだ知識や経験を活かし、日頃の生活における防災・減災に役立つ講習を実施しています。

講師
日本赤十字社大阪府支部
事業部参事(防災教育事業担当)
西田 節夫氏
講師略歴
日本赤十字社大阪府支部において、AEDを用いた救命手当や、三角巾を用いた応急手当など救急法講習の普及に努め、救急法指導員の養成も行っている。現在は、防災教育事業を担当し、防災・減災についての講習普及に従事している。

講師
講師略歴
「学校安全から考える危機管理-防犯、防災を主として-」
大阪教育大学では、学校安全に関する危機管理や安全対策についての研修や講演会を数多く開催しています。学校安全の中での危機管理や安全対策は、児童・生徒の尊い命を守るための普段からの重要な行動規範・行動指針になるとともに、地域や民間企業などの危機管理・安全対策とも多く共通しています。
今回のセミナーでは、主に防犯・防災に関する危機管理や安全対策について、本学の取り組み事例を中心に紹介します。
講師
大阪教育大学
教育学部教育協働学科・教授
学校危機メンタルサポートセンター長・教授
藤田 大輔氏
大阪教育大学
教育学部教育協働学科・准教授
学校危機メンタルサポートセンター・准教授
後藤 健介氏
大阪教育大学
教育学部教育協働学科・准教授
学校危機メンタルサポートセンター・准教授
豊沢 純子氏
「防災のユニバーサルデザイン」
自然災害は、必ず起こります。自然の驚異をどのようにして減災に繋げるのかを考え、備えをしましょう。避難所の課題は沢山ありますが、最も大きな課題は、多様な人が避難できることです。要援護者が遠慮して避難所に行けないのではなく、要援護者に少しの配慮があれば、誰でも避難できます。

講師
プチハウスなな/LLPユニバーサルデザイン企画 代表
栂 紀久代氏
講師略歴
2004年 プチハウスなな起業
2005年 大阪産業大学大学院 UD担当講師
2006年 NPO法人サン・クラブ設立
2012年 「要援護者の防災」講演活動開始
「鈴与グループの事業継続の取り組み 〜事前対策、訓練事例の失敗例を含めて〜」
東海地震、南海トラフ巨大地震等で大きな被害が予測されている静岡県に本拠地を置き、関連会社約140社のグループ全体で事業継続に取り組んでいる鈴与株式会社の事業継続に係るプロジェクトの立ち上げからの経緯、事前対策としてのハードの整備や対策本部の作り方、具体的な訓練事例等について失敗例を交えて取り組み体制を紹介する。
講師
鈴与株式会社 危機管理室 室長
後藤 大輔氏
協力:リスク対策.com(新建新聞社)
講師略歴
大学卒業後、海上自衛隊に入隊。地方総監部の防衛・警備・災害担当幕僚、護衛艦隊司令部の訓練主任幕僚、護衛艦艦長、護衛隊司令等の職を歴任。在職中は災害派遣活動やテロ対策特措法に基づく海外派遣も経験。平成24年4月に鈴与株式会社に入社後、鈴与グループの危機管理を統括する危機管理室長としてグループの事業継続体制の強化、推進に従事。
「ドローンの利活用と今後の展望について」
今、ドローンを使ったイノベーションが進んでいます。
その分野は輸送・測量・災害救助分野など多岐に渡り、私たちのこれからの暮らしを大きく変える可能性を秘めています。
今回のセミナーでは、そのドローンを使って何ができるのか?
これからの展望について最新の情報をお伝えさせていただきます。
講師
一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会
代表理事
坂口 博紀氏
講師略歴
平成11年から京都、東京を中心にフリーランンスの雑誌、広告カメラマンとして活動
平成22年10月広告撮影の事業を中心とする株式会社ミクスメディア設立
平成24年6月よりドローンを用いたPV撮影を開始
多数の大手企業の空撮案件を経験。
現在までの総フライト時間は2000時間を超える。
「『災害からの安全な京都づくり条例』と災害危険情報の整備・提供について(仮題)」
京都府では、平成28年8月、[1]府が災害危険情報を提供し、府民等と情報共有、[2]防災機能を強化し、災害に強いまちづくりを推進、[3]地域防災力の向上の3つを柱とする「災害からの安全な京都づくり条例」を施行しました。
この条例を踏まえ、洪水や地震、土砂災害等の災害危険情報を重ねて閲覧できる「京都マルチハザード情報提供システム」を整備し、多くの府民に活用していただけるよう取組を行っています。
講師
京都府
府民生活部 防災消防企画課 課長
山田 直人氏
![]()